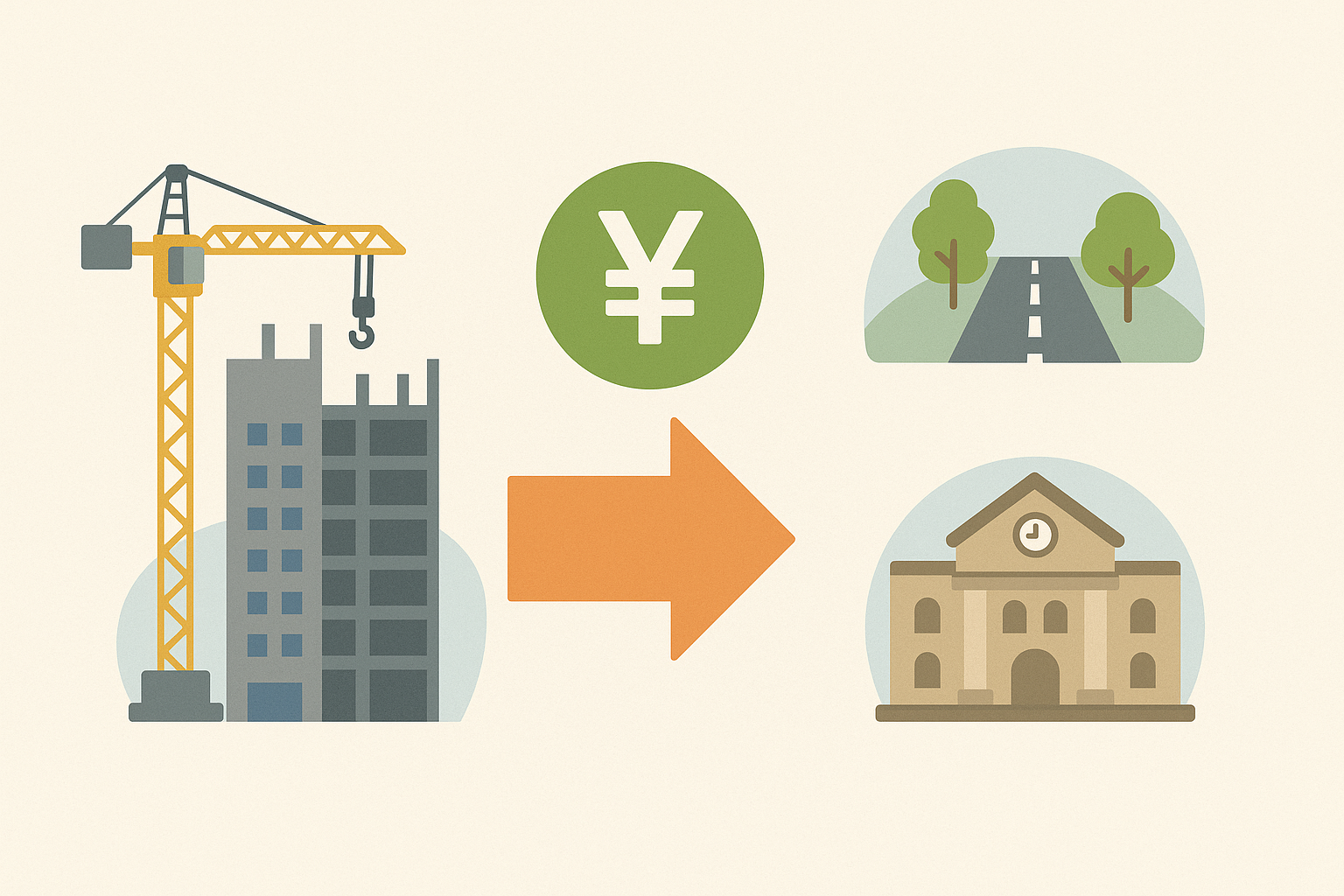背景:開発利益の地域社会に対する還元の必要性
ソウル市では、大規模な都市開発による土地価値の上昇に伴い生じる開発利益を地域社会に還元し、公平な都市インフラの整備を図ることが重要な課題であったところ、韓国の国会は2021年1月に「国土計画法」を改正し、第52条の2として「公共施設等の設置費用」に関する規定を新設した。この規定により、開発行為に伴う利益の一部を徴収し、未整備インフラの整備や公共施設の確保に充てる法的根拠が整備された。
なお、この改正以前からソウル市では開発許可時に公的貢献として公共施設用地の提供や費用負担を条例に基づき求める運用があったが、法的な明確性に欠けていた。国土計画法への明文化により法的安定性が確保され、開発利益還元の制度運用は条例依存から法定の仕組みに移行したと言える。
制度の構造
ソウル市の「公共施設等設置基金」は、上記の法改正に基づき設計された制度である。その基本的な構造は次の通りである。
まず、都市計画の変更によって民間の開発可能容積が増加したり建築規制が緩和された場合(例えば用途地域の変更による容積率の緩和や、都市計画施設の変更による建築制限の緩和が生じるケース)には、開発事業者等に対し、地域内の公共施設等を整備またはその敷地を提供する義務が課される。この公共施設等には、国土計画法上「公共施設」(第52条の2第1項第1号)「インフラ施設」(同項第2号)および「公的賃貸住宅や学生寮等で公共的必要性が認められる施設」(同項第3号)が含まれる。整備義務の水準(施設規模や用地面積)は、開発による土地価値の上昇分の範囲内で定められることが法律で明示されており(同項本文)、具体的には計画変更前後の当該地の公示地価の差額を基準として算定される。このように土地価格上昇分を上限とする仕組みとすることで、過度な負担とならないよう配慮されている。
もっとも、開発区域内ですでに必要な公共施設等が十分に確保されていると認められる場合には、実物の提供に代えて費用の納付(金銭貢献)に振り替えることが可能である(同条第2項)。その判断は市長等が建築委員会・都市計画委員会の共同審議を経て行うこととされ、開発区域内の既存公共施設の充足状況や、開発による人口・交通量の変化に伴う需要増などの要素が考慮される。区域内に不足がないと専門家委員会が認めた場合、開発事業者は区域外の公共施設整備プロジェクトに充当する費用を納付することで義務を果たすことができる。費用を充当できるプロジェクトは法律上あらかじめ限定されており、「長期未執行の都市計画施設の設置事業」(同項第1号)、「上記公共的必要施設(例:公営住宅や学生寮)の設置事業」(同項第2号)、「その他公共施設またはインフラ施設の設置事業」(同項第3号)のいずれかに該当するものと定められている。このように、区域内に直接施設を整備しない場合でも、その資金を他地域の不足する公共インフラ整備に充てる仕組みにすることで、広域的な都市基盤の充実と均衡ある発展に資するよう制度設計がなされている。
納付された金銭貢献は、市と区の双方に配分される点も本制度の特徴である。法律によれば、特別市(ソウル市)の管轄区域で本制度に基づく費用徴収が行われた場合、その費用のうち「20%以上30%以下」の範囲で各開発区域ごとに定められた割合に相当する額が開発区域の属する自治体(区)に帰属し、残りが市に帰属する(同条第3項、施行令第46条の2第4項)。この配分ルールにより、開発利益の一部は開発が行われた区に還元されつつ、相当部分が市全域のインフラ整備財源としてプールされる形となっている。
さらに第52条の2第5項では、納付された費用の使用基準等について地方自治体の条例で定めるよう委ねている。これを受けてソウル市は都市計画に関する条例および基金条例を整備している。
ソウル市の「都市計画条例」第22条が基金の使途基準等に関する規定である。同条第1項で「公共施設等の設置費用」の優先使用基準が定められており、法律第52条の2第5項に基づき長期未執行の都市計画施設事業を最優先に充当することなどが規定されている 。こうした使途制限は、市全体として喫緊の課題である未整備インフラへの投資を促すとともに、開発が行われた地域において計画だけ存在していた施設(道路や公園等)の早期実現を図る意図がある。
また、ソウル市の「公共施設等設置基金条例」は、上位法である国土計画法第52条の2第4項および都市計画条例第22条の委任に基づき制定されたもので、基金の設置目的や管理・運用方法を定めている。同条例第1条(目的)では、法令の規定に基づき基金を造成し、その運用に必要な事項を定めることを目的としている。さらに基金の存続期間(同条例第4条)、財源構成(第5条)、支出範囲(第6条)、そして基金運用審議委員会の設置(第8条~)などが規定されている。
おわりに
ソウル市の公共施設等設置基金の制度設計には、日本の自治体にとっても示唆に富むいくつかの工夫が盛り込まれている。
- 第一に、開発利益に応じた負担設定である。負担額の上限を「土地価値の上昇分」という客観的な指標に連動させた点は、恣意的な負担徴収を避ける工夫である。事業者にとっても合理的かつ予見可能な範囲での負担となり、過度な負担感を和らげる効果がある。他方、行政にとっては地価上昇分を的確に評価する仕組み(公認の不動産鑑定評価)が必要となるが、韓国では法律に鑑定評価法人等による評価手続きを明記することで担保している。
- 第二に、基金によるプールと広域配分である。開発地点ごとに現物施設を整備させるのではなく、一旦金銭で徴収し基金でプールすることで、都市全体の優先課題に資金を振り向けられる柔軟性を持たせている。ソウル市では、特に長期未執行インフラの解消が喫緊の課題であったため、市レベルで集めた資金を投じて大規模な道路や公園整備に充当できるようにしている。一方で開発区にも一定割合を還元し、地域独自の課題にも対応できるよう市区間で配分している点は、広域自治体と基礎自治体のバランスを取った設計といえる。
- 第三に、使途の優先順位付けである。法律および条例で長期未執行施設への優先充当を義務づけたことにより、開発利益が他の用途に流用されず本来の目的に沿って使われるよう担保し、老朽・未整備インフラが後回しにされがちな問題に対応している。
本事例は、日本の地方自治体が開発利益還元の制度設計を検討する上で有益な参考となろう。ソウル市の事例が示すように、法的根拠の明確化、公平かつ効率的な資源配分、そして制度目的に合致した運用の担保が重要である。